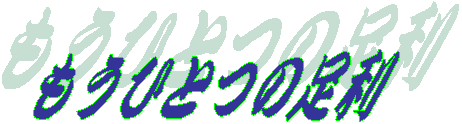 |
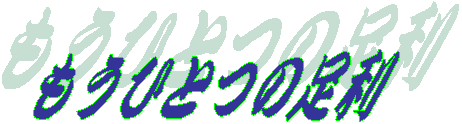 |
|
足利工業大学の光と風の広場
風車に関しては、世界的な第一人者 牛山先生の風車の実験施設をに太陽光と水と木(木材)などの自然環境とエネルギーについての施設として一般公開したものです。広場については24時間いつでも公開していますが、ミニミニ博物館は、火・木・土の10時から3時までの公開です。開かれた大学を目指してか、とても嬉しく思います。 H13・6・9撮影 |
 |  |  |
| 風車の広場 いろいろな風車の実験施設です |
風車の羽のモニュメントの奥は、 青空教室です。 | 風車と太陽光についてのミニ博物館です |
 |
本物の風車が出来ました。 2005・5撮影 市制80周年で足利市が東武足利市駅前に造ったのは モニュメントになってしまいましたが 足利工大が本物の風車を造りました。下の方には太陽光発電の装置もあります。風車と太陽電池で発電した電力は、近くにある足利工大総合研究センターの電気として使っているそうです。立派なものです。 |
|
|
山 川 長 林 寺
足利市の山川町にある曹洞宗福聚山長林寺。ご本尊に釈迦三尊を祀り、観音霊場としては千手観音があります。 池を挟んで山の中腹の崖に道了様の赤いお社があります。 |
||
 |  |  |
 |  |
JR足利駅
単線で電車の本数も少ないローカル線の小さな駅ですが、 地元の人は両毛駅と呼んでいます。 ちょっと寂しい気もしますが、足利の歴史を感じるいい所です。 |
|
今のJR両毛線は、繊維の町足利の地元の豪商たちが設立した両毛鉄道株式会社から始まります。 明治時代 東北線の計画時点で豪商たちは、路線を足利を通すように政府に嘆願しました。しかし、東京と軍隊がある宇都宮を最短距離で結びたかった軍部の主張で現在のようなルートになりました。鉄道なしでは世界の足利(両毛)になれないと考えた豪商たちは、自分たちで鉄道を通す事を考えました。それが両毛鉄道株式会社です。後に国鉄に売却されましたが、良き日の足利を伝える武勇伝だと考えます。 昔 両毛線を走っていたEF60 123も置いてあります。 |
||
|
臨済宗萬壽山光明寺
ぼたん寺として有名ですが、境内にいろいろな石仏や道祖神などがありとってもいいところです。近くにこころみ学園もあります。
2002年4月27日撮影 |
|||
 |  |  |  |
|
足利の変なお祭り(初山) 毎年6月1日に渡良瀬橋南岸にある 浅間山(せんげんやま)山頂の神社で 子供の成長を願って おでこにハンコを捺す儀式があります。男浅間と女浅間という2つの山があって 毎年たくさんの親子ずれが参拝に集まります。 |  | 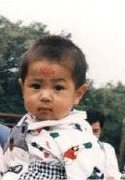 |  |
|
渡良瀬川の風景です。渡良瀬橋と中橋の中間・左岸(北側)に森高千里の渡良瀬橋の歌碑が出来ました。駐車場もなく歩く人は犬の散歩の 人くらいですが、人が近ずくとセンサーが感知して「渡良瀬橋」の歌が流れます。渡良瀬橋をバックに夕日はきれいな場所ですが、もう少し・・・・ |
||
 |  |  |
渡良瀬橋と織姫山 | 森高千里の歌で有名になった渡良瀬橋 | 足利の中心 中橋と三本杉です。 |
 |
鏡 岩
足利のハイキングコースにある鏡岩です。
織姫から20分くらいのところにアリ両崖山の 下にあります。西渓園のからも登っていけます。 岩登りの練習が出来そうなところですが、 小さな子どもづれでも楽しいところです。 2002年3月10日撮影 |
 |  |  |  |
|
西場の百観音
前列が西国・中列が坂東・後列が秩父の観音に由来している。 江戸時代中期の作といわれている。 |
樺崎八幡宮
足利義兼が母の供養のために作った寺と 八幡宮を合祀したもの |
樺崎八幡宮にある 発掘調査中の義兼の慰霊塔 H13・5・26撮影 |
|
 |
日光神社の大杉
(名草町)
根元は1本に見えますが、5本の杉の木がまとまったもので、上のほうで分かれています。地元では、神が宿ると信じられていて、御神木として祀られています。 |
|
ココファームワイナリー
知的障害者の施設こころみ学園が障害者の自立の ために作ったワイナリー。2階のテラスでチーズでも つまみに1杯、最高です。 |
園生たちの働くブドウ畑。園長の川田先生の著書 ブドウ畑の笑顔で有名になりました。 H13H13・5・27撮影 |
 |  |
|
行道山浄因寺
714年に行基上人により開創された修行場 足利3大将軍義満により祈願寺として整備された 臨済宗の名刹 |
寝釈迦
浄因寺の奥の院 行基上人の骨が分骨されて
あるらしい。 H13・5・27撮影 |
 |  |